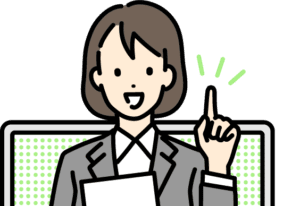【不動産の相続】相続税と不動産評価、税理士と司法書士の連携で安心サポート
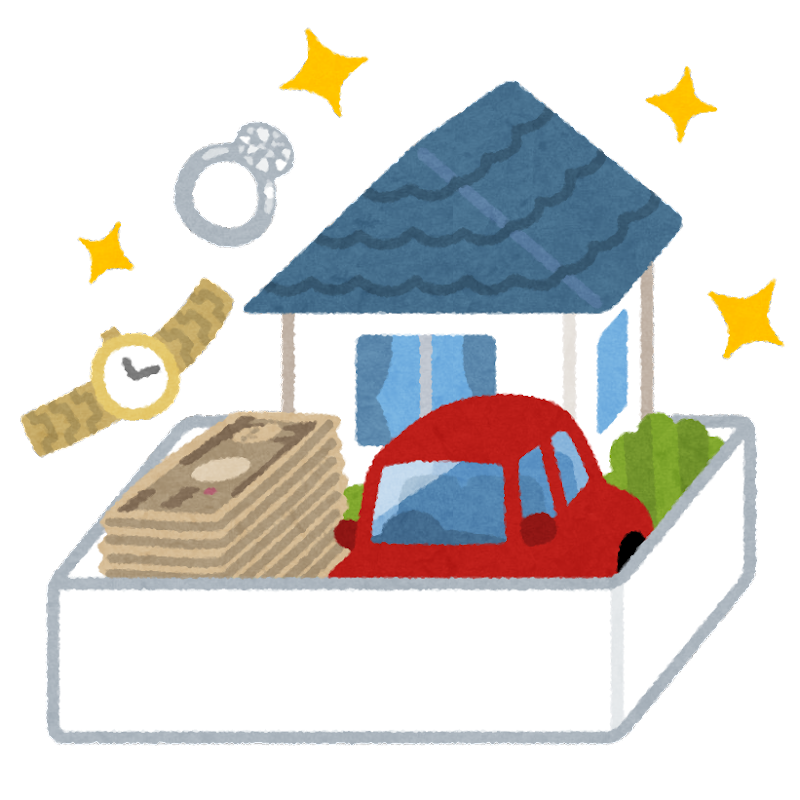
相続手続きの中でも、その後の税金についてご心配される方は多くいらっしゃいます。相続財産に不動産が含まれることは多く、私たち司法書士が相続登記(不動産の名義変更)のご依頼を最も多く受ける分野の一つでもあります。
今回は、相続における税金の問題、特に相続税を検討する上での不動産の評価、そして私たち司法書士と税理士がどのように連携して皆様をサポートできるのかについて、より詳しくご説明いたします。
目次
相続と税金:司法書士ができること、税理士との連携
相続において気になるのが「相続税」ではないでしょうか。
相続税は、亡くなった方から財産を相続したときに、その財産の価額に応じて課税される税金です。ただし、誰でも必ず相続税を支払わなければならないわけではありません。相続税には「基礎控除」というものがあり、相続財産の総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税の申告も納税も必要ありません。
基礎控除額の計算方法
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合、基礎控除額は 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円 となります。この金額を超える場合に、相続税の申告・納付の検討が必要になります。
相続税申告における不動産の評価
相続財産の中でも、不動産(土地や建物)は評価額が大きくなることが多く、相続税の計算において非常に重要です。司法書士は、相続登記の専門家として不動産に深く関わりますが、相続税申告における不動産の評価については、税理士の専門的な知識が必要です。
- 建物の評価: 一般的に、建物は固定資産税評価証明書に記載されている「固定資産税評価額」をそのまま用いることが多いです。
- 土地の評価: 土地の評価はより複雑です。
- 路線価方式: 市街地などでは、道路に面する宅地の1平方メートルあたりの価額である「路線価」が国税庁から公表されており、これに基づいて評価します。
- 倍率方式: 路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に国税庁が定める一定の「倍率」を乗じて評価します。
- 土地評価の難しさ: 土地の形状(不整形地、間口が狭い土地など)や利用状況によっては、評価額の補正が必要になることがあります。このような複雑なケースや、より正確な評価が求められる場合、土地の評価は税理士でないと難しいのが実情です。税理士は、これらの要素を考慮し、適切な評価額を算出します。
私たち司法書士は、相続登記のために固定資産評価証明書などを取得し、財産の概要をお客様と確認しますが、相続税申告のための詳細な不動産評価や税額計算は税理士の業務範囲となります。
司法書士と税理士の役割分担と連携

弊所にご依頼いただいた場合、相続手続きと相続税の申告は、それぞれの専門家が担当しますが、円滑に進めるために、密接な連携をいたします。
- 司法書士(槐事務所):
- 相続人の確定、遺産分割協議書の作成、そして不動産の相続登記や預貯金・株式の相続手続きなど、相続財産の名義変更手続きを中心に行います。
- 財産目録の作成サポートや、不動産の評価に必要な資料(登記事項証明書、固定資産評価証明書、公図、地積測量図など)の収集を行います。
- 相続財産を正確に把握し、誰が何を相続するのかを法的に確定させることで、相続税申告の基礎を固めます。
- 税理士:
- 相続税の節税対策(各種特例の適用検討など)や納税資金に関するアドバイスも税理士の専門分野です。
- 不動産を含む相続財産の詳細な評価、相続税の具体的な計算、相続税申告書の作成、税務署への提出といった税務に関する専門的な手続きを行います。
司法書士は税金の専門家ではありませんので、具体的な税額の計算や税務相談、相続税の申告代理を行うことはできません。しかし、相続手続きの初期段階からお客様と関わる中で、相続税申告の必要性の有無を大まかに判断したり、必要に応じて信頼できる税理士をご紹介したりすることが可能です。
特に不動産を相続された場合、相続登記は司法書士が、相続税申告は税理士が担当しますが、評価の前提となる物件の特定や権利関係の整理は司法書士が行った情報が基礎となります。弊所では、お客様のご希望に応じて税理士と緊密に連携を取り、相続手続きから相続税申告までの一連の流れを円滑に進められるようサポートいたします。
多摩市で相続のお悩みは、当事務所にご相談ください
私たち司法書士は、「街の法律家」として、皆様の暮らしに密着した法的なサポートを提供しています。皆様が、相続に関する手続きはもちろん、それに伴う不動産の評価や税金の問題で不安を感じたり、どこに相談すれば良いか分からなかったりする場合には、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所では、お客様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、相続手続き全般から、必要に応じた税理士との連携まで、最適な解決策をご提案いたします。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、まずはお電話やメールでお問い合わせいただければ幸いです。
まとめ:相続は早めの準備と専門家への相談が鍵
相続は、法務と税務が複雑に絡み合う分野であり、特に不動産が含まれる場合にはその評価や税金の計算が専門的な知識を要します。相続税の申告が必要かどうか、不動産の評価はどうなるのか、といった疑問は早めに専門家に相談することが大切です。
私たち司法書士は、相続手続きの専門家として、そして税理士をはじめとする他の専門家との窓口として、皆様の相続が円滑に進むよう全力でサポートいたします。不動産の相続登記から、その後の税金のご心配まで、安心してご相談ください。
初回のご相談は無料です!042-319-6127受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。