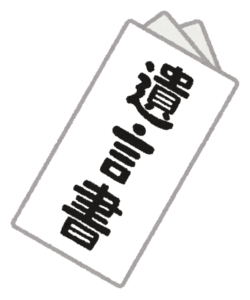【司法書士解説】相続人が海外在住。印鑑証明書がない!どうする? – サイン証明で解決!
ご家族が亡くなられ、相続の手続きを進める中で、「相続人の一人が海外に住んでいる」というケースは、国際化が進む現代において決して珍しくありません。
相続手続き、特に遺産分割協議(遺産の分け方を決める話し合い)がまとまった際には、「遺産分割協議書」という書類を作成し、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付するのが日本の一般的なルールです。
しかし、相続人が日本国籍であっても、海外に長年住んでいて日本に住民票がない場合、印鑑登録がないため、印鑑証明書を取得することができません。
「印鑑証明書がないと、遺産分割協議書が作れないの?」
「相続手続きが進められないのでは?」
と、ご不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。
でも、ご安心ください。このような場合でも、「サイン証明(署名証明)」という方法で、印鑑証明書の代わりに手続きを進めることが可能です。
目次
なぜ印鑑証明書が必要なの?
まず、なぜ遺産分割協議書に実印と印鑑証明書が必要なのか簡単にご説明します。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約・名義変更など、様々な相続手続きで必要となる重要な書類です。
この書類に押された印鑑が、確かに本人の意思で押されたものであることを公的に証明するために、実印とその印鑑が本人のものであることを証明する印鑑証明書が必要とされています。
海外在住だと印鑑証明書が取れない?
印鑑証明書は、日本の市区町村役場で印鑑登録をしている人に対して発行されます。
印鑑登録は、その市区町村に住民登録(住民票)があることが前提です。
そのため、たとえ日本国籍の方であっても、海外に生活の拠点を移し、日本の住民票を抜いている(非居住者である)場合は、印鑑登録ができず、印鑑証明書を取得することができません。
解決策は「サイン証明(署名証明)」!
そこで登場するのが「サイン証明(署名証明)」です。
これは、海外にある日本の大使館や領事館で発行してもらえる証明書です。
サイン証明とは?
申請者本人が、領事担当官の目の前で書類(遺産分割協議書など)にサイン(署名)します。
そのサイン(署名)が、確かに申請者本人のものであることを領事が証明してくれる、というものです。
このサイン証明が、日本における印鑑証明書の代わりとして法的に認められています。
手続きの流れ(概要)
事前準備

まずは、手続きを行う予定の在外公館(お住まいの地域を管轄する日本大使館・領事館)に、必要書類や手続き方法、予約の要否などを確認しましょう。
パスポートなどの本人確認書類が必要になります。
書類への署名
在外公館に出向き、領事担当官の面前で、用意した遺産分割協議書などの書類にサインをします。事前にサインしていくのではなく、必ず領事の前で行う必要があります。
証明書の発行
サインが本人のものであることが確認されると、サイン証明書が発行されます。
サイン証明には、署名した書類と証明書が一体になった形式や、署名が本人のものであることだけを単独で証明する形式などがあります。
どちらの形式が必要かは、遺産分割協議書を提出する先(法務局、金融機関など)に事前に確認しておくとスムーズです。
日本での手続き
発行されたサイン証明書を、遺産分割協議書に添付して、他の相続人の実印・印鑑証明書とともに提出することで、不動産の相続登記や預貯金の解約などの手続きを進めることができます。
注意点
時間
海外との書類のやり取りには国際郵便などで時間がかかる場合があります。早めに準備を始めましょう。
費用
サイン証明の発行には手数料がかかります。
専門家への相談
海外在住の相続人がいる場合、手続きが通常より複雑になることがあります。
書類の準備や他の相続人との連携など、ご不安な点があれば、私たち司法書士のような相続の専門家にご相談いただくことをお勧めします。スムーズな手続きのためのお手伝いができます。
まとめ
相続人の中に海外にお住まいの方がいらっしゃる場合でも、印鑑証明書が取得できないからといって相続手続きを諦める必要はありません。
「サイン証明」という制度を利用すれば、問題なく手続きを進めることが可能です。
ただし、個別の事情によっては他の注意点が必要になることもあります。相続手続きでご不明な点、ご心配な点がございましたら、どうぞお気軽に専門家である司法書士にご相談ください。
初回のご相談は無料です!042-319-6127受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。