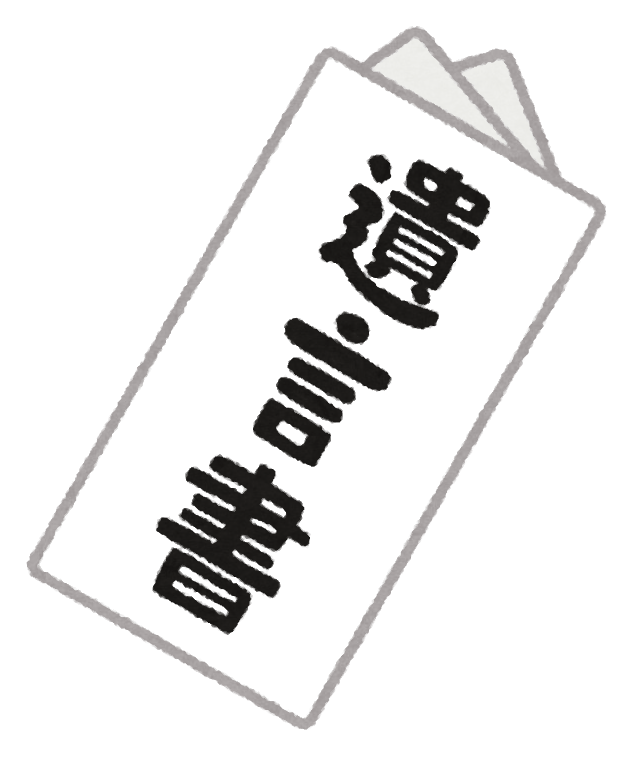遺言書はいつから準備する? 知っておきたい基本と注意点
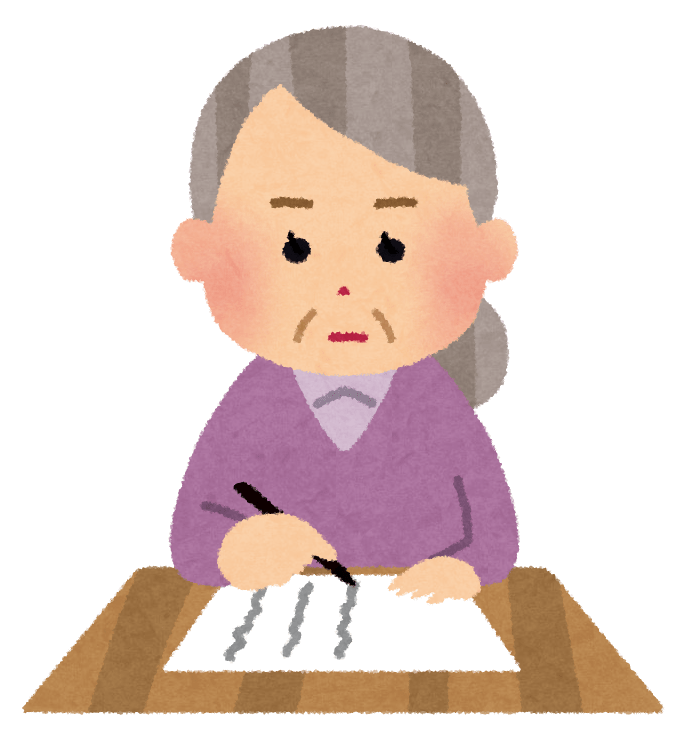
「終活」という言葉も一般的になり、ご自身のエンディングについて考える方が増えています。その中でも「遺言書」は、ご自身の財産を誰にどのように遺したいかという最終意思を示す大切なものです。しかし、いつ頃から準備を始めれば良いのか、一度書いたら変更できないのかなど、疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回は、遺言書に関する基本的な知識と、準備する上での注意点をわかりやすく解説します。
目次
遺言書はいつから書ける?
実は、遺言書は満15歳になれば誰でも作成することができます。意外と早くから書けることに驚かれるかもしれません。「まだ若いから」「財産もそんなにないし」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、遺言書の準備は早すぎるということはありません。例えば、万が一の事故や病気は予測できません。ご自身の意思を明確に残しておくことは、残されたご家族にとっても安心に繋がります。
一度書いた遺言書も書き直せる?
「一度遺言書を書いたら、もう変更できないのでは?」と心配される方もいらっしゃいますが、ご安心ください。遺言書は、後から何度でも内容を訂正したり、新しく書き直したりすることができます。これは、ご自身で作成する自筆証書遺言だけでなく、公証役場で作成する遺言公正証書であっても同様です。また、前に作成した遺言が自筆証書遺言で、新しく遺言公正証書を作成するといったように、訂正する遺言の形式に制約もありません。
ただし、大切な注意点があります。遺言書を訂正する方法は、法律で厳格に定められています。法律に則った方法で訂正しなければ、その訂正が無効になってしまう可能性があります。ご自身で訂正される場合は、専門家にご相談いただくのが確実です。
遺言書の書き換えすぎには注意も必要
遺言書は後から訂正できるとはいえ、あまりにも頻繁に内容が変更されていると、思わぬところで手続きが滞ってしまうケースも考えられます。
これは経験則になりますが、相続手続きの際に金融機関などが「これだけ頻繁に書き換えられているということは、まだ他にも新しい遺言書が存在するのではないか?」と警戒し、相続手続きがスムーズに進まないということも実際に起こり得ます。もちろん、最新の有効な遺言書が優先されるのが原則ですが、無用な混乱を避けるためにも、熟慮した上で作成し、頻繁すぎる書き換えは控えた方が賢明かもしれません。
遺言書作成後に状況が変わったら?知っておきたいポイント
遺言書は、作成した時点でのご自身の意思や財産状況に基づいて書かれます。しかし、時間と共に状況が変化することは十分にあり得ます。例えば、財産の内容が変わったり、遺言書で財産を渡そうと考えていた相手の状況が変わったりすることなどです。そのような場合、遺言書の効力はどうなるのでしょうか。
遺言書に書かれていない財産はどうなるの?
たとえば、遺言書を作成したときには持っていませんでしたが、後から財産を取得したとすれば、一体どうなるのでしょうか。
遺言書に記載されなかった財産については、原則として、法定相続人が法律で定められた相続分(法定相続分)に応じて分け合うことになります。具体的には、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合って決める必要があります。
全ての財産について遺言で指定したい場合や、将来取得する財産を含める場合には、遺言書に「その他一切の財産を〇〇に相続させる(または遺贈する)」といった包括的な文言を入れておく方法があります。このような記載をしておくことで、遺言書作成時に把握していなかった財産や、後から出てきた財産についても、ご自身の意思を反映させることが可能になります。ただし、包括的な記載が有効かどうかは、遺言の形式や他の記載内容との関連も影響するため、専門家への相談をおすすめします。
遺言書に書いた財産は処分できないの?
「遺言書で特定の財産を誰かに遺すと決めたら、その財産はもう自由に処分できなくなるの?」と疑問に思われるかもしれません。
結論から申し上げますと、遺言書に記載した財産であっても、遺言者ご本人が生前にそれを売却したり、誰かに贈与したりすることは自由に行えます。 遺言書を作成したからといって、ご自身の財産の処分が制限されるわけではありません。
ただし、注意点があります。遺言書に書いた財産を生前に処分した場合、遺言書の中でその財産に関する部分は、原則としてその効力を失います。 例えば、遺言書で「長男にこの不動産を相続させる」と書いていたとしても、その不動産をご自身が生きている間に売却してしまえば、長男はその不動産を相続することはできなくなります。
ご自身の意思と遺言の内容に食い違いが生じないよう、財産状況に変化があった場合は、遺言書の見直しも検討すると良いでしょう。
遺言書で財産を渡すはずだった人が先に亡くなってしまったら?
遺言書で「妻に全財産を相続させる」と書いたものの、万が一、妻がご自身より先に亡くなってしまった場合、その遺言はどうなるのでしょうか。この場合、妻に財産を相続させるという部分は効力を失います。つまり、法定相続によって相続手続きが行われることなります。
このような事態に備えて、予備的な遺言条項を設けておくことをお勧めします。例えば、「妻に全財産を相続させる。ただし、妻が私より先に死亡した場合は、長男に全財産を相続させる」といったように、次に財産を相続する人(次順位の受遺者)を指定しておくのです。これにより、ご自身の意思をより確実に実現することができます。
まとめ
遺言書は、ご自身の思いを形にする大切な手段です。作成に、早すぎるということはありません。また、一度作成した後でも、状況の変化に合わせて内容を見直すことができます。
しかし、法的に有効な遺言書を作成し、ご自身の意思を確実に実現するためには、法律の専門家にご相談いただくことをお勧めします。司法書士法人槐事務所では、皆様の状況に合わせた最適な遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です!042-319-6127受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。