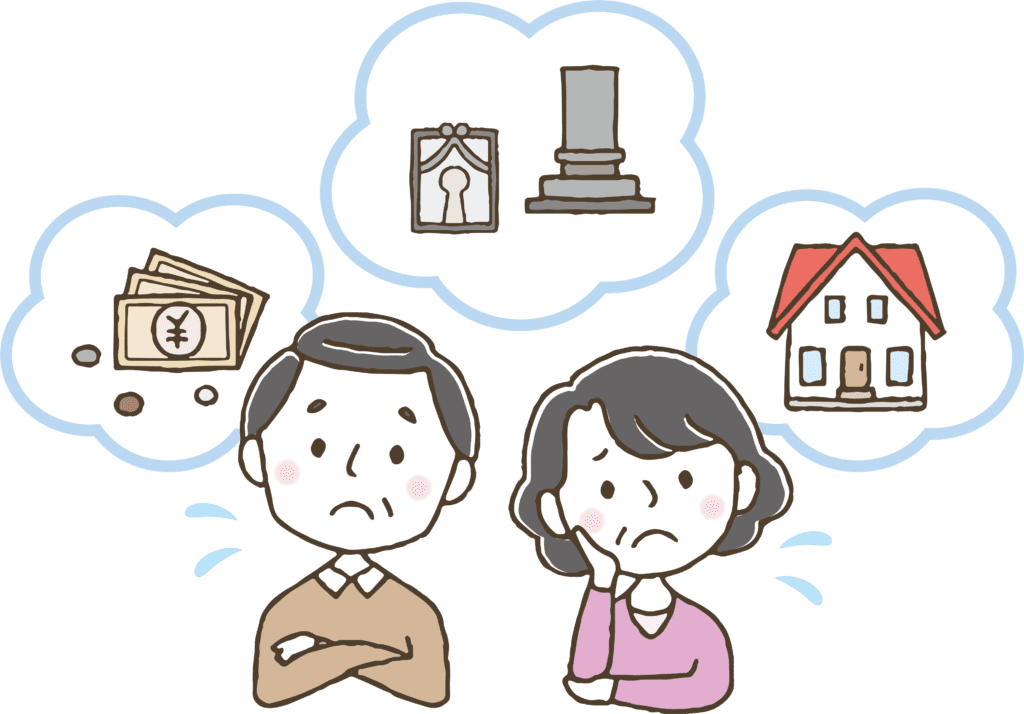
「今は元気だけど、将来認知症になったらどうしよう…」
「もしもの時、大切な財産管理や身の回りのことを誰に託せばいいのだろう…」
こんなご不安はございませんか?
超高齢社会を迎え、誰もが認知症や病気によって判断能力が低下する可能性に直面する時代です。そんな将来の不安に備えるための制度の一つに「任意後見制度」があります。
この「任意後見制度」について、司法書士がわかりやすく解説します。ご自身の将来のため、そして大切なご家族のために、ぜひ最後までお読みください。
目次
任意後見制度って?司法書士が分かりやすく解説
まず、成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分になってしまった方を法的に支援する制度です。成年後見人は、ご本人に代わって契約を結んだり、財産を管理したり、生活に必要な手続き(身上監護)を行ったりします。
法定後見制度との違いは?
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
- 法定後見:すでに判断能力が低下してしまっている場合に利用する制度です。 家庭裁判所が、ご本人の判断能力の程度に応じて「補助」「保佐」「成年後見」のいずれかに分類し、それぞれ補助人・保佐人・成年後見人を選任します。
- 任意後見:まだ判断能力がしっかりしている方が、将来の判断能力の低下に備えて利用する制度です。 ご自身が信頼できる相手を選び、将来どのような支援をしてもらいたいかをあらかじめ契約で決めておくことができます。
つまり、「任意後見制度」は、ご自身の意思で、将来の後見人や支援内容を事前に決められる、オーダーメイドの備えと言えるでしょう。
任意後見制度のメリット・デメリット
任意後見制度には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
- 自分で後見人を選べる:ご自身が最も信頼できる人(ご家族、ご友人、専門家など)を任意後見人に指定できます。
- 自分の意思を最大限反映できる:将来どのような支援を受けたいか、財産をどう管理してほしいかなど、ご自身の希望を契約内容に盛り込むことができます。
- 柔軟な支援が可能:他の契約(見守り契約や任意代理契約など)と組み合わせることで、法定後見よりも柔軟な支援体制を築くことができます。
デメリット
- 取消権がない:法定後見とは異なり、ご本人の判断能力が無くなってしまったときに行った不利益な契約を、任意後見人が後から取り消すことはできません。
- 任意後見監督人への報酬が発生する:任意後見が開始されると、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され、その監督人への報酬が別途発生します。この報酬額は裁判所が決定します。
- 公正証書での契約が必須:任意後見契約は、必ず公正証書で作成しなければなりません。
- 契約内容が登記される:作成された任意後見契約の公正証書の内容は、法務局で登記されます。
任意後見制度はいつから始まるの?
任意後見契約を締結しても、すぐに効力が発生し、財産管理がはじまるわけではありません。実際に任意後見が開始されるのは、ご本人の判断能力が低下した後になります。
具体的な流れは以下の通りです。
- ①医師の診断
- 判断能力が衰えてきたと感じたら、医師の診断を受けます。
- ②家庭裁判所への申立て
- 任意後見人になる予定の方(任意後見受任者)などが、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」を行います。
- ③任意後見監督人の選任と任意後見の開始
- 家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見が開始されます。
- ④任意後見人による支援
- 任意後見人は、任意後見監督人の監督を受けながら、契約内容に基づいてご本人を支援します。
任意後見契約の解除について
締結した任意後見契約を解除することも可能ですが、そのタイミングによっては、手続が異なるため、注意が必要です。
- 任意後見監督人選任前:ご本人または任意後見受任者のどちらからでも、公証人の認証を受けた書面によって解除することができます。
- 任意後見監督人選任後:正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することができます。
任意後見契約等のご依頼をいただく場合の流れ
私たちに任意後見契約書やその他の関連契約書の作成、そして公正証書作成の支援をご依頼いただく際の一般的な流れは以下の通りです。安心してご相談ください。
槐(えんじゅ)事務所では、お客様お一人おひとりの状況と想いに寄り添い、丁寧に対応させていただきます。
- ①初回ご相談(初回のご相談は無料です)
- まずはお電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。お客様の現在の状況、将来へのご希望や不安な点などを詳しくお伺いします。任意後見制度をはじめ、お客様に合った制度やお手続きについて、わかりやすくご説明いたします。
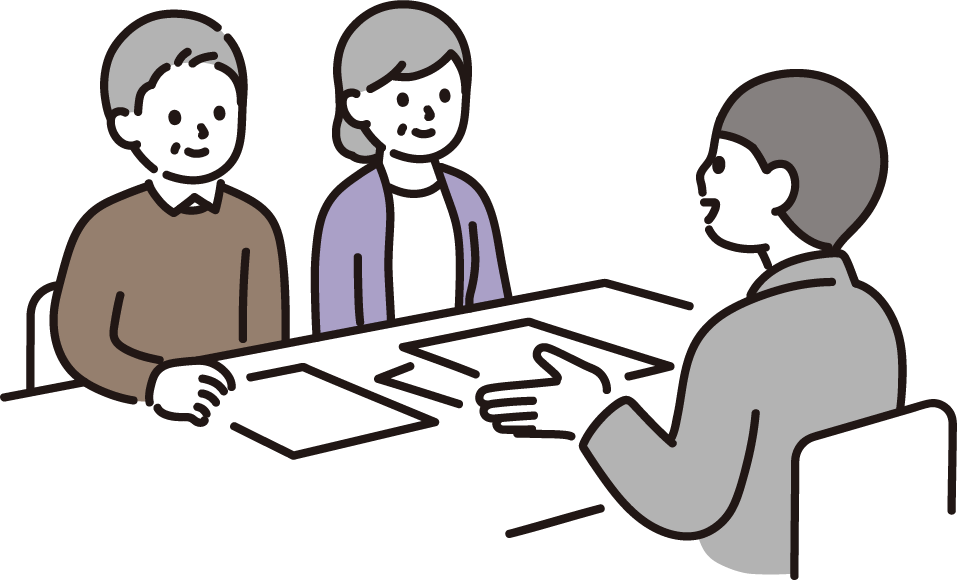
- ②ご提案・お見積り
- ご相談内容に基づき、最適な契約内容のプラン(任意後見契約に加えて、見守り契約や財産管理契約、死後事務委任契約などを組み合わせるかなど)をご提案します。
また、必要となる手続き、期間、費用について明確なお見積りを提示いたします。
- ③契約内容の打ち合わせ・設計
- ご提案内容にご納得いただけましたら、具体的な契約内容について詳細な打ち合わせを行います。
将来の任意後見人に誰を指定するか、どのような支援を希望されるかなど、お客様の意思を最大限に尊重し、きめ細かく契約書案に反映させていきます。
- ④契約書案の作成・確認
- 打ち合わせ内容に基づき、司法書士が契約書の案を作成します。作成した契約書案をお客様にご確認いただき、修正点や追加のご希望があれば調整いたします。
- ⑤公証役場との調整・予約
- 任意後見契約は公正証書で作成する必要がありますので 、当事務所が公証役場との間で、公正証書作成のための手続きや日時の調整を行います。
必要書類の収集についてもサポートいたします。
- ⑥公正証書の作成
- 公証役場にて、お客様、任意後見受任者様、そして公証人の前で契約内容の確認を行い、公正証書を作成します。原則として当事務所の司法書士も同席し、手続きがスムーズに進むようサポートいたします。
- ⑦契約後のフォロー
- 作成された公正証書の謄本をお渡しし、今後の流れや保管方法などについてご説明します。
任意後見契約の効力が発生するまでの間も、ご不安な点についてのご相談を承ります。
任意後見契約と一緒に検討したい契約
任意後見契約の効力をより確実なものにしたり、判断能力が低下する前から支援を受けたりするために、以下のような契約を任意後見契約と合わせて締結することがあります。
- 見守り契約:任意後見契約の効力が発生するまでの間、定期的に連絡を取り合ったり、訪問を受けたりすることで、健康状態や生活状況を把握してもらい、適切な時期に任意後見監督人選任の申立てをしてもらうための契約です。 これは任意後見契約とは別の契約になります。
- 任意代理(財産管理)契約:判断能力はまだ十分にあるものの、病気や身体の障がいなどで財産管理や各種手続きが難しくなった場合に備える契約です。 契約内容に従って、財産管理などの支援を受けることができます。 こちらも任意後見契約とは別の契約です。
- 死後事務委任契約:ご本人が亡くなられた後、任意代理契約や任意後見契約は終了します。 その後の葬儀、納骨、役所への届け出、未払いの入院費の清算などの事務手続きを委任する契約です。
これらの契約を組み合わせることで、ご自身の状況や希望に合わせた、よりきめ細やかなサポート体制を築くことが期待できます。
将来の安心のために、専門家にご相談ください

任意後見制度は、ご自身の意思を反映した将来の備えとして非常に有効な手段です。しかし、契約内容の検討や公正証書の作成など、専門的な知識が必要となる手続きも多く、少し複雑に感じられるかもしれません。
私たち司法書士は、任意後見契約はもちろんのこと、見守り契約、任意代理契約、死後事務委任契約、そして遺言書の作成など、皆様の将来の安心のためのトータルサポートを行っています。
「自分にはどんな備えが必要なんだろう?」 「任意後見制度についてもっと詳しく知りたい」 「信頼できる専門家に相談したい」
このようにお考えの方は、ぜひ一度、槐事務所にご相談ください。皆様の想いに寄り添い、お一人おひとりに最適なプランをご提案させていただきます。
初回のご相談は無料です!042-319-6127受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。